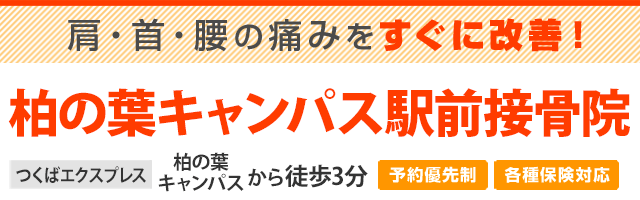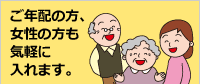巻き肩

こんなお悩みはありませんか?

肩こりがひどい
日常生活において肩こりがひどく、肩周りに重だるさを感じることがある。
姿勢が悪いと言われる
立っている時や座っている時に、「姿勢が悪いね」「座っている時に背中が丸くなっているよ」と言われたことがある。
呼吸が浅い気がする
日常生活や就寝時に、呼吸がしっかりとできていないように感じることがある。
体が疲れやすい
短時間の仕事や日常動作でも、すぐに体が疲れてしまうことがある。
頭痛が出たり、睡眠の質が低い気がする
頻繁に頭痛が起こったり、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、しっかり眠れた感じがしなかったり、疲れが取れない感覚が残ることがある。
巻き肩について知っておくべきこと

まず、巻き肩とは簡単に言うと、肩が丸まった状態のことです。本来であれば耳の延長線上にあるはずの肩が、前方に出てしまっている状態を指します。現代社会においては、長時間のデスクワークやスマートフォンの長時間利用により、肩から胸にかけての筋肉が収縮してしまい、その結果として巻き肩へとつながることがあります。
主な症状としては、姿勢の乱れや、肩周辺の筋肉が固まることによる血流の悪化などが挙げられます。それにより、自律神経の乱れ、頭痛、眼精疲労などが現れることもあります。
巻き肩と猫背は似たような印象を持たれることがありますが、猫背は肩周りだけでなく、背骨の前弯や全身の前傾姿勢に関係するため、巻き肩とは異なる症状となります。ただし、巻き肩の状態が進行してしまうと、猫背を併発する場合もあります。
症状の現れ方は?

症状の現れ方として多いのは、首や肩周りの慢性的な痛みです。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用が続くことで、肩周りの筋肉が硬くなりやすくなります。その状態が習慣化することで、肩の痛みとともに肩こりが起こり、慢性化することがあります。
さらに、これらの肩の不調が進行することで、肩から首にかけての血流が低下し、頭痛を引き起こす可能性があります。また、巻き肩によって肩や胸の筋肉が縮まり、胸郭の動きが制限されることで呼吸が浅くなる場合もあります。結果として、酸素の取り込み量が減少し、体が疲れやすくなったり、集中力が低下してしまうことも少なくありません。
その他の原因は?

その他の原因として、日常生活における首や肩周りのストレッチやトレーニング不足が関係していることが考えられます。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用が巻き肩の症状につながることが多いですが、これは同じ姿勢を長時間続けることで起こります。
同じ姿勢でいると、首や肩周りの血流が悪くなり、慢性的な痛みや首こり、肩こりといった症状が現れることがあります。そのため、普段の生活の中で首や肩周りのストレッチやトレーニングを取り入れることで、身体の血流を促進し、長時間の作業による症状の軽減が期待できる可能性があります。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩を放置すると、首や肩周りの慢性的な痛みが悪化し、身体への負担が大きくなってしまいます。就寝時には、肩が内側に巻き込まれる影響で胸郭の動きが制限され、肺活量が減少するため呼吸がしづらくなることがあります。
また、首や肩周りだけでなく背中の筋肉にも負荷がかかり、慢性的な背中の痛みにつながることがあります。これにより背中が丸まり、猫背になる可能性も考えられます。
さらに、肩が前方に移動することで、肩の前側の筋肉が強く縮こまり、神経や血管が圧迫されることがあります。その結果、手にしびれが出る「胸郭出口症候群」を発症する可能性もあります。
当院の施術方法について

当院での施術方法は、主に胸部と肩周りにアプローチいたします。肩が内側に巻き込まれることで胸部や肩周りの筋肉が固くなっているため、それらの筋肉を緩めるよう施術を行います。
胸の筋肉に対するアプローチとしては、「猫背矯正」や「上半身ストレッチ」をご提案いたします。猫背矯正は胸部だけでなく肩甲骨にもアプローチが可能なため、胸部から背部にかけて施術を行い、症状の軽減を目指します。
また、肩に対しては「肩甲骨はがし」をご提案し、肩周りの筋肉だけでなく肩甲骨にもアプローチすることで可動域を広げ、肩周りの血流促進により症状の軽減が期待できます。
軽減していく上でのポイント

巻き肩の症状を軽減していくためには、セルフケアの重要性をご理解いただくことがポイントです。巻き肩は日常生活での負担が積み重なることで症状が現れるため、当院での施術だけでなく、ご自宅でのセルフケアや職場の合間に行うストレッチやトレーニングが症状の悪化や負担の軽減につながります。そのため、院外でのセルフケアやストレッチの指導を行い、その必要性や関連性について改めてご説明し、重要性を理解していただきます。
また、患者様一人ひとりの症状やニーズを十分に把握した上で施術や対応を行い、患者様がご自身の身体の状態を正しく認識できるよう寄り添いながら、一緒に取り組んでいくことが大切です。
監修

柏の葉キャンパス駅前接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:福島県
趣味・特技:トレーニング、バレーボール観戦、映画鑑賞