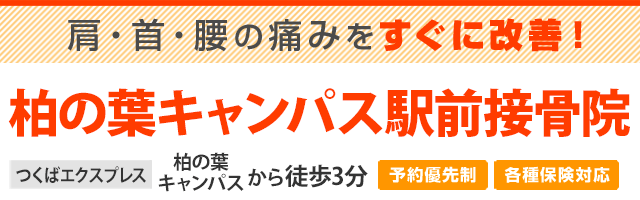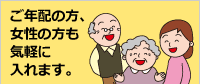肉離れ

こんなお悩みはありませんか?

太ももやふくらはぎに痛みがある
→太ももの前側や後ろ側、ふくらはぎの後ろ側の筋肉に痛みが出ている。
太ももやふくらはぎに窪みがある
→損傷の程度によっては太ももやふくらはぎを触ると凹んでいるのがわかる。
太ももやふくらはぎの部位に内出血のようなものがある
→太ももやふくらはぎの部分に腫れや皮下出血(あざ)のような症状がある。
足を曲げたり伸ばしたりしたら痛みが出る
→膝を曲げたり伸ばしたり、足首を曲げたり伸ばしたりすると太ももやふくらはぎに痛みが発生する。
肉離れをして歩行が困難である
→歩行時や走った際に太ももやふくらはぎに痛みが発生する。
肉離れで知っておくべきこと

肉離れという言葉は俗称で、正式には「筋挫傷」と呼ばれる症状です。好発部位は太ももの前側(大腿四頭筋)、太ももの後ろ側(ハムストリングス)、太ももの内側(内転筋)、ふくらはぎの後ろ側(腓腹筋)など、下半身の筋肉で発生することが多いです。
発生要因として多いのは、スポーツ競技中に急な無理な動作を行ったことで筋肉に急激な収縮が起こる場合です。準備運動を入念に行わないことで筋肉の柔軟性が不足した状態で運動をすると、筋繊維が充分に伸び縮みできず、肉離れの発症につながりやすいと考えられます。
症状の現れ方は?

肉離れの主な症状には、疼痛、皮下出血、損傷部の陥没などがあります。損傷部に圧痛を加えると強い痛みが生じ、さらに損傷部の筋肉に収縮運動をさせると、同様に強い痛みが発生します。そのため、歩行時に体重がかかると痛みによってうまく歩行ができなくなることがあります。
また、筋繊維の切れた部分には腫れや皮下出血(あざのようなもの)が見られる場合があります。肉離れの損傷の程度によっては、損傷部位が凹んでいるのが目視で確認できたり、触ってみて凹んでいることがわかったりすることもあります。
さらに、肉離れをした際には、「ブチッ」や「バチッ」といった断裂音が聞こえる場合もあります。
その他の原因は?

肉離れの発症のその他の原因として考えられるのは、スポーツなど激しい運動をする前に行うウォーミングアップ(準備運動)の不足や、体内の水分が不足し、その結果筋肉に必要な水分が足りず柔軟性が低下した状態で運動を行うことです。
また、睡眠不足や栄養不足など、身体のメンテナンスを十分に行わないことで筋肉の疲労が蓄積することや、筋肉量の増加や減少に伴う変化も原因の一つとされています。
成長期などでは、骨格や筋肉量の変化により肉離れが発生しやすくなります。さらに、外因的要因として、冬場など外気温が低い際に外で運動を行うことも発症の原因になる場合があります。
肉離れを放置するとどうなる?

肉離れはスポーツ障害として後遺症が出やすい症状とされています。
肉離れが発生した際に、歩ける状態であっても損傷の程度に関係なく適切な応急処置や施術を受けずに放置してしまうと、症状が進行し、柔軟性や筋力が低下して運動機能が衰える可能性があります。さらに、損傷部が「血腫」になったり、しこり(瘢痕組織)が形成されてしまい、動かす際に痛みやつっぱり感が生じることがあります。
また、このような状態を放置すると、周囲の筋肉にも負担がかかり、同じ部位の肉離れが再発したり、反対側の部位で新たに肉離れが発生するリスクが高まる恐れがあります。
当院の施術方法について

当院の施術方法としましては、まず肉離れを発症した際に損傷部位に炎症が確認できた場合、その部位に対して冷却を行います。冷却により腫れや内出血、痛みなどを軽減することができます。
症状が緩和されてきた後は、電気療法や鍼、ハイパーナイフ、テーピング、筋膜ストレッチなどを用いて、損傷部位や周囲の筋肉にアプローチを行い、血流の改善を促進して回復力を高めます。
さらに、再発防止や予防のために自宅で行うストレッチなどのセルフケアを指導し、スポーツや日常生活でのパフォーマンスが低下しないよう、それぞれの患者様に合った施術を提案させていただきます。
改善していく上でのポイント

改善していく上でのポイントは、しっかりと状態を見極めて施術を進めていくことです。何がどのように影響を与えているのかを探り、症状が軽減するように原因をしっかりと見つけていくことが重要です。
一回の施術だけではなく、数回にわたる施術を行い、患者様との信頼関係を築き、その患者様に合った施術や原因を見つけ出します。
その時の症状の軽減も重要ですが、その先のアフターケアや再発予防につながる施術を行うことが大切です。症状が軽減されたことをゴールとせず、その先の日常生活でのパフォーマンス向上を目指すことが重要です。
監修

柏の葉キャンパス駅前接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:福島県
趣味・特技:トレーニング、バレーボール観戦、映画鑑賞